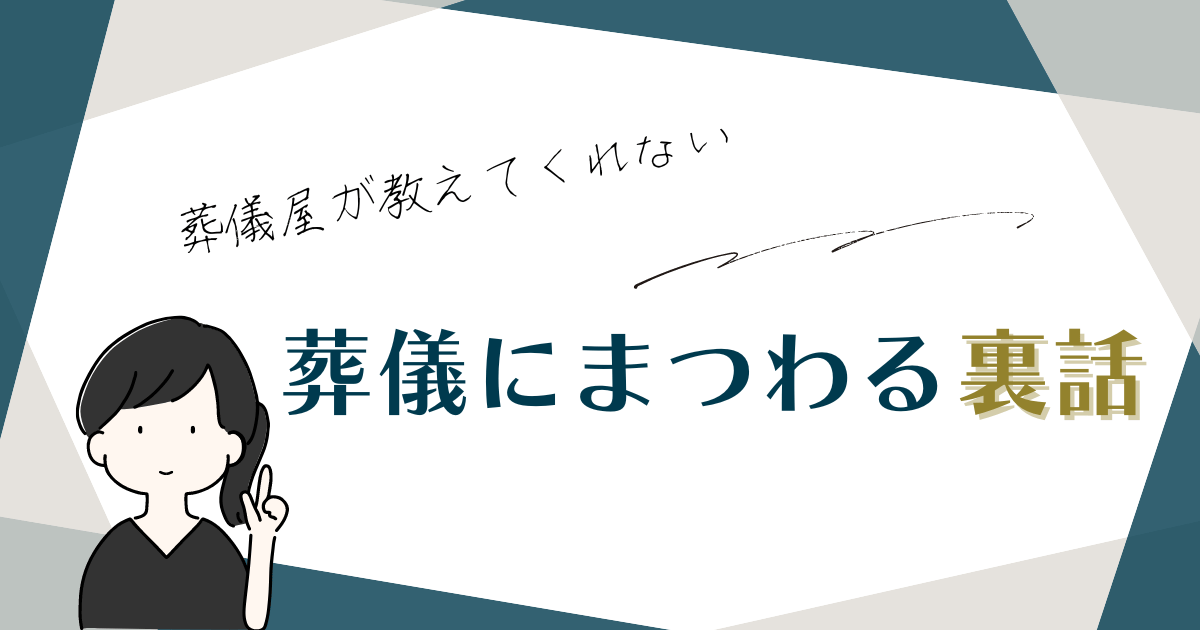【宗祖】
親鸞
【開宗年】
1224年
【本山】
宗派により異なる
本願寺派…本願寺(西本願寺)
大谷派…真宗本廟(東本願寺)
高田派…専修寺
など
【ご本尊】
阿弥陀如来
脇侍
向かって右…開祖『親鸞』
向かって左…中興の祖『蓮如』
【名号】
南無阿弥陀仏
【根本経典】
『浄土三部経』
『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』
『仏説観無量寿経(ぶっせつかんむりょうじゅきょう)』
『仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)』
【焼香作法】
※押しいただかない
1回…本願寺派など
2回…大谷派など
3回…高田派など
【線香作法】
1本をこちらから見て左側に点火部分が来るように寝かせる。
【法名】
戒名ではなく法名
([院号])釋(尼)[法名]
【概要】
浄土真宗とは、法然の弟子である親鸞が、法然の教えを継承して開かれた宗派です。
教団として発展したのは親鸞の没後で、親鸞が著した『顕浄土真実教行証文類(けんじょうどしんじつきょうぎょうしょうもんるい)』が草稿された年である1224年を開宗年として定めています。
浄土真宗は時代により、一向宗(いっこうしゅう)や門徒宗(もんとしゅう)と呼称されました。
現在でも門徒さんと言えば浄土真宗を信仰している人を指す呼び名です。
浄土真宗の最も重要な教義は、『他力本願(たりきほんがん)』という教えです。
他力本願とは、自己の力や善行ではなく、阿弥陀仏の慈悲によって救われるという信仰で、人間の無力さや罪深さを認識し、阿弥陀仏の救済に頼ることが重要視されます。
また、善人は自己の能力で悟りを開こうとし仏に頼ろうとする気持が薄いが、煩悩にとらわれた凡夫(悪人)は仏の救済に頼るしかないとの気持が強いため、阿弥陀仏に救われるとした、「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」という一文で有名な悪人正機(あくにんしょうき)と言われている教えがあります。
『般若心経』は自力の教えを説くお経なので、浄土真宗では唱えません。
浄土真宗では、即得往生 住不退転(そくとくおうじょう じゅうふたいてん)といって、現世において自己の力に頼ることなく、ただ念仏を唱えることで阿弥陀仏の救済を直ちに受け、来世で浄土に生まれることができるとされます。
このため、浄土真宗の教えでは冥土の旅や十王審判はありませんので、追善供養も行いません。
年忌法要やお仏壇へ手を合わせるのは、阿弥陀仏への信心を捧げるために行います。
浄土真宗の法要では、浄土三部経などのお経の他に、宗祖親鸞の教えである、『正信偈(しょうしんげ)』が唱えられます。