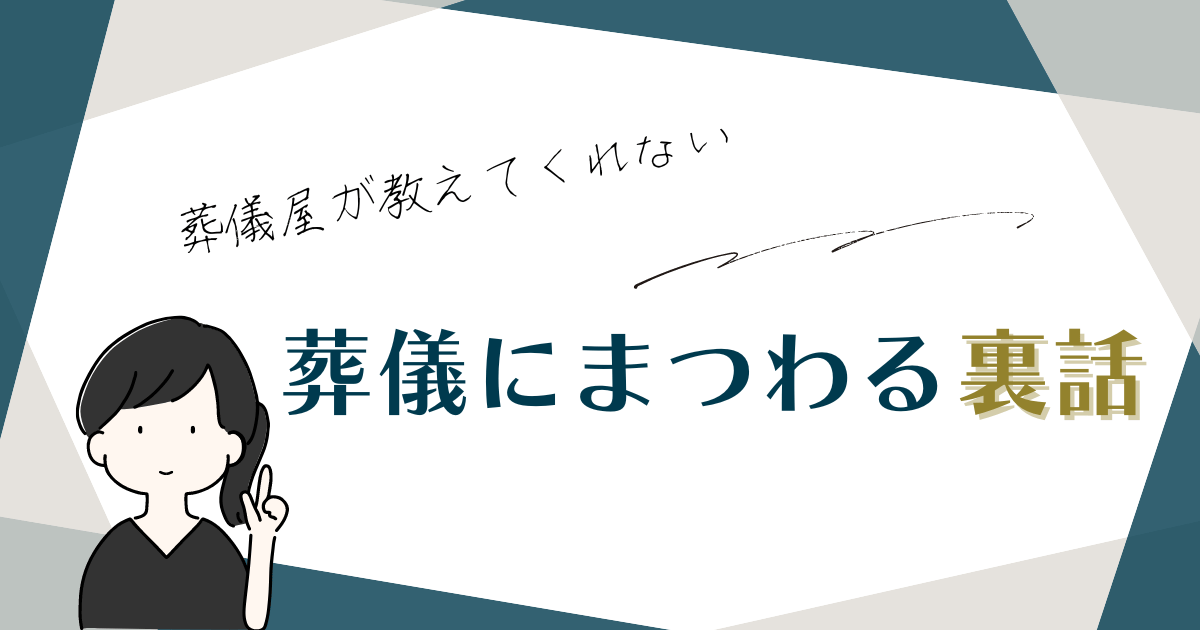『南無阿弥陀仏』や『南無妙法蓮華経』など、仏教では、頭に『南無』とつくことが多くあります。
この『南無』、読み方は「なむ」や「なも」など宗派により若干の違いがありますが、サンスクリット語(インドの古代語)の「ナマス」に音写、音を当てただけの漢字なので、漢字に意味はありません。
「ナマステー」とはインドでの挨拶の言葉ですが、「ナマス」とは敬礼する、という意味、「テー」は貴方に、という意味です。
ナマス=『南無』とは、信仰心を表す最上級の言葉になります。
南無を日本語に直すと、「お願いします」や「信じています」などになりますが、それらの言葉では足りない、絶対的な信仰の力が含まれており、仏教用語の「帰依(きえ)する」や「帰命(きみょう)する」という言葉になります。
『南無阿弥陀仏』ですが、『阿弥陀(あみだ)』というのはサンスクリット語で、「アミターバ」=はかりしれない光を持つ者という意味をもつ仏様の名で、西の彼方にあるとされる極楽浄土という仏様の国の教主とされます。
仏様の世界にも《菩薩(ぼさつ)》や《明王(みょうおう)》などと呼ばれる、位や役割のようなものがあり、阿弥陀様は仏様の世界でも最高位の『如来(にょらい)』と呼ばれる位なので、『阿弥陀如来』と呼ばれます。
『南無阿弥陀仏』とは阿弥陀如来に強い信仰の力でお願いする、という意味の言葉で、「なむあみだぶつ」や「なもあみだぶつ」と読み、漫画やコントなどで「なんまいだー」と唱えているのは実はこの『南無阿弥陀仏』だったりします。
このように、仏様の名前をとなえることを『称名(しょうみょう)または、唱名(しょうみょう)』と言い、となえる仏様の名前を『名号(みょうごう)』と言います。
『名号』をとなえることで仏様に帰依し仏様の救済を願いご利益があるものと考えられています。
仏教でも浄土宗や浄土真宗という宗派はこの阿弥陀如来に帰依することで極楽浄土へと導いてもらうことを教義とする宗派です。
浄土宗や浄土真宗では、阿弥陀如来こそが信仰の対象であり、ご本尊となります。
『本尊(ほんぞん)』とは、寺院や仏壇の主に中央に祀られる、最も大事な信仰の対象となる、彫刻や絵画などの偶像のことで、『名号』を本尊とする場合もあります。
また、ご本尊の左右には、『脇侍(きょうじ、または、わきじ)』といって、ご本尊を補佐する役割の、偶像が祀られ、三体を合わせて三尊と呼びます。
何を三尊とするかは、宗旨や宗派により異なります。
天台宗
本尊は地域や寺院により様々ですが、『阿弥陀如来』や『釈迦如来=仏教の開祖いわゆるお釈迦様』が多いようです。
脇侍は
向かって右に中国の天台宗開祖『智顗(ちぎ)』
向かって左に日本の天台宗開祖『最澄(さいちょう)』
名号は『南無阿弥陀仏』
真言宗
本尊は『大日如来(だいにちにょらい)』
脇侍は
向かって右に真言宗の開祖『空海(くうかい)』
向かって左に『不動明王(ふどうみょうおう)』
名号は『南無大師遍照金剛(なむたいしへんじょうこんごう)』
遍照金剛とは空海のことです。
浄土宗
本尊は『阿弥陀如来』
脇侍は
向かって右に中国の浄土宗開祖『善導(ぜんどう)』
向かって左に日本の浄土宗開祖『法然(ほうねん)』
名号は『南無阿弥陀仏』
浄土真宗
本尊は『阿弥陀如来』
脇侍は
向かって右に浄土真宗開祖『親鸞(しんらん、)』
向かって左に浄土真宗中興の祖『蓮如(れんにょ)』
名号は『南無阿弥陀仏』
臨済宗
本尊は『釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)』=釈迦如来=お釈迦様
脇侍は
向かって右に『達磨大師(だるまたいし)』
向かって左に『観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)』
名号は『南無釈迦牟尼仏』
曹洞宗
本尊は『釈迦牟尼仏』
脇侍は
向かって右に曹洞宗開祖『道元(どうげん)』
向かって左に曹洞宗中興の祖『瑩山(けいざん)』
名号は『南無釈迦牟尼仏』
日蓮宗
本尊は『十界曼荼羅(大黒天)』と言って、開祖日蓮が創始した曼荼羅です。
脇侍は
向かって右に『鬼子母神(きしもじん)』
向かって左に『大黒天(だいこくてん)』
大黒天
名号は『南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)』