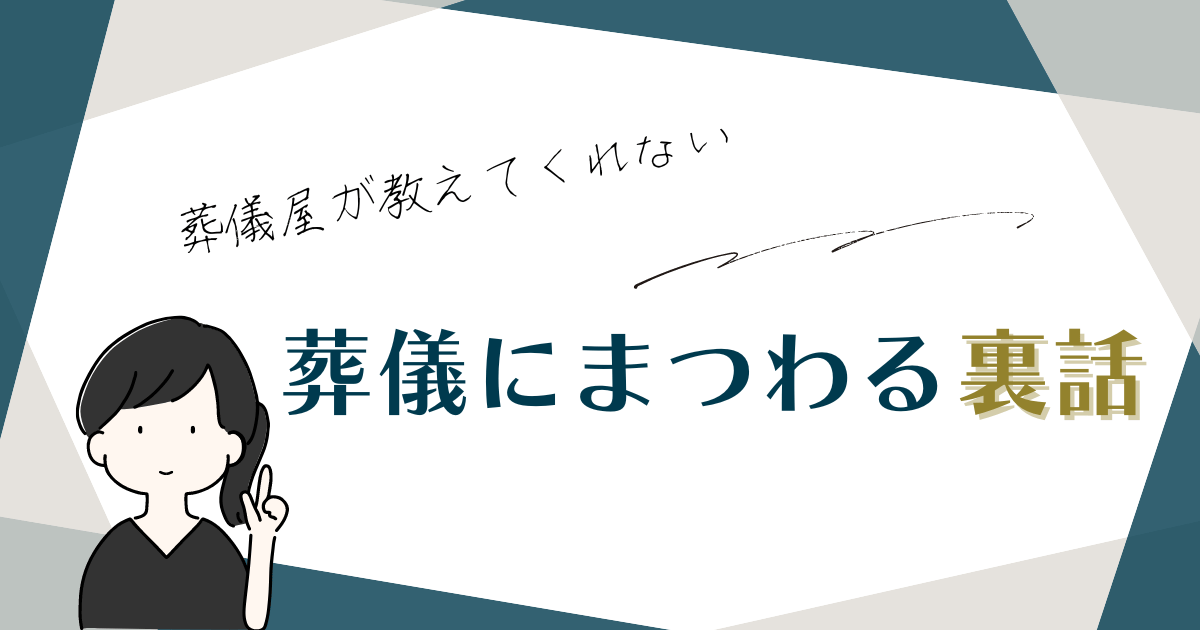【日本での開祖】
栄西
【開宗年】
1191年
【本山】
妙心寺
南禅寺
建長寺
建仁寺
など
【ご本尊】
釈迦如来
脇侍
向かって右…『達磨大師』
向かって左…『観世音菩薩』
【名号】
南無釈迦牟尼仏
【根本経典】
特になし
【焼香作法】
1回
【線香作法】
1本に火をつけ真ん中に立てます
【戒名】
([院号])[道号][戒名][位号]
【概要】
臨済宗は、達磨大師から数えて11代目の祖師である臨済義玄禅師を宗祖と仰ぐ『禅(ぜん)』の教えを受け継ぐ宗派です。
日本には、栄西が比叡山で天台宗の教えを学んだ後、宋に留学、臨済宗黄龍派の教えを学び、1191年に帰国後、布教を開始しました。
禅の教え、とは坐禅(ざぜん)を中心とした修業により全ての人間に本来備わっている仏性を呼び覚ます=悟りに到達することを目的としており、阿弥陀如来による他力救済の教えを受け継ぐ浄土宗などとは、真逆と言っていい教えです。
このため、浄土宗や浄土真宗は主に公家や一般庶民、農民に広まったのに対し、自力による救済を重んじる禅宗は、同じく自力による目的達成を図る武士階級に広まります。
特に、栄西が宋から茶や建築の文化を鎌倉幕府に伝えたことで、臨済宗は幕府からの庇護を受け、鎌倉武士を中心に広まりました。
臨済宗は、『公案(こうあん)』と呼ばれる、いわゆる禅問答を解いて悟りに至る『看話禅(かんなぜん)』という修行法が行われます。
臨済宗や曹洞宗の葬儀では、導師が突然
「かあぁぁぁぁぁつっっ!!!」
と大きな声を出します。
「喝(かつ)」と言っており、故人が現世への未練を断ち切り仏の道へ正しく進ませるための大事な作法なのですが、初見では驚きすぎて思わず声が出てしまったり、お子さんが泣き出したりします。
導師がおもむろに立ち上がると、間もなく喝タイムなので、お腹に力を入れて耐え忍ぶことをお勧めします。
曹洞宗の開祖である道元は栄西の孫弟子に当たります。